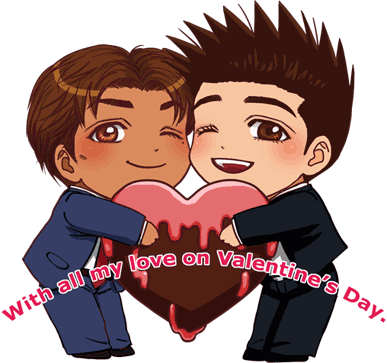|
You're my Valentine. |
|
|||||
|
正月が過ぎるとスーパーもコンビニも一斉にバレンタインへディスプレイをチェンジする。 赤やピンク、焦げ茶色が彩るチョココーナーの横を通り過ぎながら、仙道彰は昨年のバレンタインが過ぎた頃を。まだ恋人になってくれて間もない牧紳一その人を、初めて自分の部屋に招いた時を詳細に思い出していた。 * * * * * 玄関ドアを開ければ即、お義理ばかりの小さな台所と膝までしかない小さな冷蔵庫が見える。その向かいには狭いユニットバスへの扉。更に進めばメインの七畳一間。 一人暮らしにはよくある間取りの室内だろうに、ソファがわりにすすめたベッドへ腰かけた牧は忙しく視線を彷徨わせていた。仙道自身もまだ自分の部屋に彼がいることに慣れず落ち着かない心持ちで、一つしかないコンロに火をつける。 気まずい沈黙ではないし、見られて困るものがあるわけではない。しかし掃除が行き届いているとは言い難いため、会話で気を引こうと試みる。 「狭くて驚いてます? 一応片付けたつもりなんすけど」 「あ、ああいや、そういうわけじゃない。すまん……じろじろ見てたようだ」 「責めたわけじゃないから、謝らないで下さいよ」 「すまん。あ、えーと……その、思っていたより片付いてて驚いたんだ」 「そう? あざす」 付き合い初めて間もないので、二人きりになるとお互い何となくぎこちない。いや、外で会うことばかりだったせいか、外でだと二人でも会話は初めから普通に弾む。だが部屋でというのは初めてで、やたらに緊張する。というより、彼の緊張が痛いほど伝わってくるせいで俺まで肩に力が入っているというのが正しいかもしれない。 納まりが悪そうな様子の彼も新鮮で可愛いけれど。これでは距離を縮めるどころではない。 「茶菓子、そこにあるやつから食えそうなの選んで下さい」 マグカップにコーヒーの粉を入れながら、TV台として使っている三段ボックスの横に置いてあるビニール袋を指してみせると、牧は「わかった」とすぐに腰を上げた。 沸いた湯を注ぐ仙道の目の端で牧の動きが止まった。ビニール袋を手に、視線はその横に置かれていた二つの紙袋と、それに入りきらなかった小箱達に注がれている。 「あー、そこにあるチョコも食いたいのあったらどれでも開けていっすよ。けど牧さんも沢山もらってるでしょ?」 だから甘いものよかしょっぱいものの方がいいかと思って、と続けながらコーヒーを小さなローテーブルへ運ぶ。 「……牧さん?」 「あ。ありがとう」 我に返ったようにコーヒーへ会釈する牧に仙道は首を傾げてみせる。 牧は少々ばつが悪そうに下唇を噛んだが、目線を紙袋へ移して再び口を開いた。 「随分ともらったもんだなと思ってさ。……持て余すくらいなら、部室に置いて皆で食えばいいんじゃないか?」 「やっかみくらうの面倒なんで。牧さんは部室に持ってくんすか?」 「いや、俺はお前ほど多くはもらわないから」 これほど頼れそうないい男がそんなわきゃないだろうと、片眉が跳ね上がったところで思い出した。 「あー…牧さんの学校って、元が男子校だから女子がすっげ少ないんでしたっけ」 「………」 また返事がない。 やけにチョコを気にするのが気にかかり、仙道は食べるつもりはなかったけれど床に積まれた小箱のひとつへ手を伸ばして開けてみた。 「ん? これ手作りか……綺麗に包装されてると開けるまで市販品と見分けつかねんだよなぁ」 独り言を零してゴミ箱へ入れると、牧がじっとこちらを見ていることに気付いた。 意味もなくチョコを開けた自分に後悔しながら言い訳を述べる。 「……食べ物粗末にしたかないんですけど」 「いや、俺もだからわかるよ。手作りは砂糖と塩を間違えていたり、歯が欠けそうなほど固かったりするものがあるからな」 「そんなんもらったことあるんだ。味見くらいしてから渡せって感じすね」 「全くだ。お前は違うのか?」 「手作りだと何入れられてるかわかんねーから怖いんで」 「身に覚えでもありそうだな」 にやりと片方の口角を上げられた。この部屋に来て初めての笑みは小憎たらしいのに可愛過ぎて、瞬間的に襲いたくなる。 「あんた一筋の俺に失礼なこと言いますねぇ」 「俺と付き合いだしたのなんて最近じゃないか。しかも周囲には知られてないわけだし?」 「……あんたもしかしてやきもち焼いてます?」 「馬鹿言うな。あんな大袋二つにも入りきらない数にやきもちなんて焼いてたら身がもたん」 馬鹿らしいと呟いて、乱暴にプリングルスを開けている彼を見る目がにやつく。 脂下がった顔に気付き眉間の皺を深くする牧へ「あんまり可愛いこと言われると困っちゃうなぁ」と調子に乗れば、中身を出して空になった筒で頭をポコリと叩かれてしまった。 照れ隠しなのか牧はスナック菓子が入ってる袋を引き寄せて、食べたいわけでもないのだろうにまたガサガサいわせている。 不満げに引き結ばれている唇に触れたいのを我慢して、仙道は提案してみた。 「ねぇ牧さん。来年はチョコ交換しません?」 「しない。やってもあれらと一緒に床へ放置されるのは御免だ」 心底嫌そうな即答に彼が先ほど何を気にかけていたかに気付き、慌てた。 「するわきゃないでしょ! あれもねぇ、床に投げ捨ててるわけじゃないんすよ。俺だって人からもらったものにはそれなりに気くらい遣いますよ。ああなっちゃったのは三袋目の底が抜けたから、二袋に無理やり詰め込んで、入らない分を床に置いただけで。それをあんたが来る直前に躓いてちょっと散らばせちまっただけなんです」 プッと小さく吹くように笑われて、必死になって自己弁護していた自分を振り返り、少々恥ずかしくなる。 「まあ俺だってそう気遣えてはいない。似たようなものだ」 零れた苦笑が柔らかくて、仙道は深く息を吐いた。 「すよねえ〜。で、話戻すけど。チョコ交換しましょうよ」 「しない」 「なんで? あんたからのチョコは神棚に供えますよ?」 「調子のいいこと言うな。この部屋のどこにそんな上等なもんがあるんだよ」 よくぞ聞いてくれましたとばかりに仙道は己の胸を指差す。 「俺の神様はここにいるから、俺の神棚はここ。あんた専用」 「お前は調子がいいのを通り越して胡散臭い……いや“嘘臭い”だな」 「ひでー。そこは素直にカッコイイと思ってくれていいんじゃね? 俺せっかくキめてみたのに〜」 やっぱり嘘くさいと笑っている牧には、もう緊張感は微塵も感じられない。それどころかリラックスしたいつもの余裕が感じられる。 仙道は楽しくなってつい、しつこいかなと思いながらも話を続けてしまう。 「ね、どんなチョコ欲しいすか? ナッツ系? プレーン系?」 チョコケーキとかの方がいっすかと問えば、牧も楽しそうに笑みを口の両端に浮かべている。 「なんでもいいよ。……いや、どうせもらうなら希望を言おうかな」 「何がいいの?」 「手作りがいいな」 我が耳を疑い、仙道は「え?」と聞き返した。 「お前の手作りならもらう、と言ったんだ」 「お……俺の手作りぃ?? さっき手作りは食わないって話してたでしょ」 「知らん人からの物はな。ホワイトデーには俺がお返しを作ってやろう」 「え〜……、料理なら簡単なやつ程度は出来なかないけど……菓子系は無理すよぉ」 「なら、いらん。市販品はお前ほどではなくとも貰っているからな」 「……あげないとあんたから手作りのお返しはないんでしょ」 恨めし気な目線を送れば、当たり前だと言わんばかりに首肯されてしまう。 「無理すんな。男同士なんだから俺達にはバレンタインなんて、もともと関係ないんだ。しなくていいじゃないか」 諭すような優しい物言いには、この先の自分達のバレンタインデーを決定づける何かが隠されているように感じる。深読みし過ぎかもしれないが、ここで引き下がっては後々絶対に後悔しそうである。 一人暮らしといえど自炊など面倒でほぼ、しない。そんな自分が、菓子作りなんて高等芸が出来るとは到底思えない。しかしやってやれないこともない……はず。女の子達に出来て俺に出来ないわけがない、よな? 「…………わかりました。手作りしますよ。そのかわり、絶対ホワイトデーはあんたも手作りを俺に下さいね」 「約束は守るさ」 そう頷いておきながら、牧は肩を軽くすくめて「お前が来年までに忘れている方に賭けるよ、俺は」などと軽くあしらった。 * * * * * 「あれが火をつけたんだよな……」 あまり表だって見せてはいないけれど、俺はかなり負けず嫌いだ。 それを知らないわけがない彼が、ああもはっきりと挑発めいた発言をしたのは。本当に俺からの手作りチョコが欲しいからに違いない。 ─── バレンタイン、絶対に喜ばせてみせるぜ! スーパーに来る前に寄った本屋で購入した薄い本が入った紙袋を手に、仙道は片方の口角を不敵に上向ける。 材料は立ち読みで覚えた。さあ、今から材料を買って、今夜はチョコ作りだ! * * * * * 今年の2月14日は都合よくも日曜日。二月の日曜午後はお互い部活がないため、仙道は牧を自宅へ来るよう約束を無事取り付けられた。 そうして迎えた当日。午前のみの部活が終わると仙道は仲間からの誘いを断り急いで帰った。帰宅するなりもらったチョコレートを入れた紙袋をクローゼットへ全て押し込み、ついでに脱ぎ散らかしていたスウェットの上下も突っ込む。 「他に牧さんが気になりそうなものは………ないな。よし」 部屋をぐるりと見回してから満足げに仙道はベッドへ腰を下ろした。 「…………必要ないよな。うん。わかってんだけど。まあその、時間まだあるし」 自分に言い訳を零すと、仙道はいそいそとベッドのリネン一式を取り替えだした。 することがなくなってしまい目を瞑っているうちに寝ていたようで、玄関の呼び鈴の音に驚いて仙道はベッドから飛び起きた。ダッシュでドアを開く。 「悪い、少し遅くなった」 「全然すよ。どーぞ入って入って」 触れた肩が僅かだが上下している。駅から走ってきたのかもしれない。別に映画などと違い、約束の時間などあってないようなものなのに。 彼の律儀さをわかってはいても、少しでも早く会いたいと思ってくれたのかななんて。勝手な考えが俺のテンションをたやすく上げる。 「お邪魔します」と行儀よく呟いて靴を脱いでるだけなのに、今すぐ抱きしめたくなるのだから困ったものだ。 コーヒーを手渡してから用意しておいた包みを牧へ差し出す。 「はい、これ。Happy Valentine’s Day!」 「え。俺にか」 牧は目を見開いてから、少し慌てたようにマグカップをテーブルに置いて受け取る。その様子が少々意外で仙道は軽く笑い零した。 「牧さん以外の誰に、この俺がチョコを手作りして渡すってんですか」 「手作りかよ」 「!? あんたの方が忘れてんじゃないすか! 去年、あんたが」 思わず勢い込んで前のめりになったが、すかさず牧に片手で止められる。 「まて。忘れてない、覚えてるって」 真面目な顔で頷かれ、肩から力が抜ければ眉尻が下がった。 「あ……そうなんだ。っあ〜焦ったぁ。手作りだから受け取って貰えないかと思った。なんすかも〜覚えてたんなら、なんで手作りに驚くんすかぁ」 「……真に受けて、しかも覚えているとは思ってなかったから?」 「ひっでー! なんすかそれ。俺、かなり頑張ったのに〜」 「いや、だってな? その台所でなんて………あ、実家で作ったとか?」 ひとつしかない簡易コンロと、食器用洗剤とスポンジ。そしてコップが一個しか置かれていない、小さなお義理程度の台所を牧は指差した。 「実家でんなことできるわきゃないじゃないすか。大騒ぎになりますよ。相手誰だとかさぁ。そこにある、その小さい、調理道具もほぼない台所で作りましたとも」 「そうか……」 返事が短過ぎて物足りなさを感じた仙道は僅かに口先を尖らせた。 仙道がコーヒーをすする間、牧は黙ってチョコを嬉しそうに見つめている。 「見てないで開けて、食って下さいよ」 「すぐ開けるのはもったいない……。神棚に供えてから開けるよ」 「牧さん家の神棚って、一階の居間の隣の部屋?」 「お前こそ忘れてんじゃねぇか。俺の神棚だってここだ」 牧は己の胸元を拳でトンと叩いてみせる。彼もしっかりと覚えていたのが伝わってきて、少し頬が熱くなった。 「……もう供えてくれたの見えたから。開けて、食ってみて。あんたが食べてるところが見たいんだ」 片方の眉を上げた牧はこちらを測るような声音で言った。 「……一個もわけてやらんぞ?」 予想外の言葉に仙道は短く声をあげて笑った。 「いーよ、いらないよ! イヤってほど味見したから」 何度か包むのに失敗した、折り目が残る包装紙を褐色の指先が慎重に解いてゆく。現れた銀色のアルミホイルに彼が微笑んだ。 「包装紙買ったまではいいけど、チョコを包む物にまでは気がまわらなくて……すんません」 「これでいいじゃないか。十分機能を果たしている」 開かれた銀紙の中にはココアをまとったゴツゴツと不格好な、大きさもまちまちなチョコの塊。 「凄いな、ナッツのチョコだろ。美味そうだ」 「見た目はアレですけど、味で勝負だから。早く食ってみて下さいよ」 「いただきます」 カリッコリッと小気味良い音をさせて食べていた牧が笑顔を向けてくる。 「美味い。普通のナッツ入りチョコと違う。上手く言えんがナッツがメインな感じ?」 「でしょ! ちょっとない感じのをあげたくてさ。アーモンドチョコは珍しくないけど、アーモンド胡桃チョコってないよね?」 「あぁ。甘過ぎないしナッツの歯ごたえがとてもいい。いくらでも食べれそうだ」 牧がナッツ類を好きなのは知っていたけれど、味も喜ばれて仙道は片腕でガッツポーズをきめる。ビターとスイート、どちらのチョコを使うか迷った挙句、両方混ぜたのだ。 「ナッツの歯ごたえ出したくてね、アーモンドと胡桃は炒って、砂糖を……」 ベッドヘッドに置いていたお菓子作りの本へ手を伸ばす。 「そうそう、これ。このキャラメリゼってのをしたんだよ。それがさぁ、水を入れたらバチバチはねやがるわ、すぐに真っ黒焦げになるわで苦労したんだ〜」 仙道が開いたページを牧が覗き込んできた。 「…………難しそうだな」 「うん。難しかった。けど、やるとやらないじゃ全然違った」 「へぇ……凄いじゃないか。これとココアの軽い苦味のおかげで、チョコの甘さがくどくなくて丁度いいのか。なるほどなあ」 「ココアはね、ほら、“茶こし”でってあるけどさ。んなもん家にないから、最初はスプーンでかけたんだ。でも酷いことになっちまって。そこでひらめいたんだよ。母親が唐揚げする時、ビニール袋に粉入れてシャカシャカ振ってたのがいんじゃないかって」 ビニール袋にココアとチョコをつっこんでね……とジェスチャーで伝えれば、牧は感心しながら何度も頷いてくれる。 嬉しくてつい、「けどねぇ、アイデアは良かったんだけど力を入れて振り過ぎたみたいで。塊が粉々になっちまったんすよ」と余計な暴露までしてしまう。 「で、どうやってまとめたんだ? 牛乳でも入れたのか?」 「いや〜、それがどうやってもまとまんなくて。結局最初から作り直し」 「そいつは大変だったなぁ。よく余分の材料があったな」 「んーん。失敗し過ぎてチョコ切れ。仕方ないから途中でコンビニ行ったんです」 「失敗し過ぎてって、そんなに大量に袋に突っ込んで振ったのかよ」 「違う違う。その前にチョコの湯煎で一回失敗して、キャラメリゼで二回で、計三回」 「そうだったのか……」 「うん。多目に材料用意したつもりだったけど。予定通りにゃいかんもんすね」 軽く笑ったのは仙道だけで、牧は居住まいを正すように背筋を伸ばした。 「苦労して作ってくれたんだな……ありがとう」 しみじみと心よりの言葉を頂いてしまい、仙道は急に羞恥に襲われて背中に汗が浮く。 「いやいやいやいや! すんません、ベラベラ調子こいて。恩着せがましいよね。……うわっマジ恥ずかしくなってきた」 ゆるりと首を振った牧が誠実な瞳を向けてくる。 「恥ずかしくなる必要はない。作る苦労も聞けた分、より味わい深くなった。感謝して食うよ」 「そ、そんな神妙な顔しないで。どんどん食って下さいよっ」 仙道は火照る頬を持て余し、自分もチョコへ手を伸ばした。が、その手はピシリと払い落される。 「やらんと言っただろうが。これは俺のだ」 「別にいいじゃん、んなチョコくらい」 「馬鹿言うな。誰がやるか」 本気で苦々しい顔をする牧に仙道は目を瞠った。 牧は「油断も隙もない……。残りは家で食う」と独りごちて、仙道から隠すように背を向け残りをアルミホイルにくるみはじめてしまった。 その背に仙道はポツリと問うた。 「……嬉しいんだ?」 こちらを振り向かないまま、牧はハンガーにかけてある自分のコートへ向かう。 「当たり前だろうが。好きな奴から初めてもらった、しかもそいつが苦労して作った初めてのチョコだぞ。これ以上貴重なものがあるか」 本気で腹立たしそうな声音が仙道の心臓の辺りをぎゅっと締めつける。 「まあ……そうだけど……」 正直そこまで喜んでくれるとは思いもしていなかった。少々売り言葉に買い言葉的な感じと、お返しの手作り菓子が欲しかったから作っただけなのに。 照れ屋の彼がこんなにもはっきりと想いを伝えてくれる。 その言葉ひとつひとつが深い恋情に満ちているから。喜びだけではなく愛しさが一気に押し寄せてきて、胸が痛いくらい熱くなった。 コートのポケットにしまってきた牧は再び隣に腰を下ろすと頭を下げてきた。 「ありがとう。お返しは俺も自作するからな」 「楽しみにしてます」 「お前ほど美味く作れるかは自信ないが、頑張ってみるよ」 「……あのさ、お返しってホワイトデーにくれるんだよね?」 「そのつもりだが?」 「図々しいってわかってるんだけど、お礼は今日もらいたいんです…」 「今日って。そりゃ無理だ。今から材料買って帰っても、慣れたものならまだしも、菓子なんて作ったことがないものを」 困り顔で弁明する牧の言を、仙道は小さく片手を上げて遮った。 「違うんです。手作りは来年のホワイトデーに下さい。俺は来年も手作りのチョコをあんたに贈るから。だから今年のお礼は。お礼……は…………」 そこまで口にしたところで、喉がつっかえてしまった。急に風船が萎んでいくように肩から力が抜けていく。 ─── 言えない。今夜は帰らずに泊まっていってくれだなんて。 客用布団なんてない俺の部屋では、必然的にこのベッドで一緒に寝てもらうしかなくて。そうなったらもう、今まで苦労して抑えに抑えつけてきた欲望は絶対に。……絶対に嫌われてしまう。こんな狭い部屋のボロベッドなんてムードのないとこで初めての夜など、絶対にダメだ。 初めての手作りをこれほど喜ぶ彼には、初めての夜はどこか綺麗でちょっと高いホテルとかじゃないといけない。やっと抵抗なくキスが出来るまでになったのに。こんな場所でガッカリさせた上にヘマこいて嫌われたら、すっげー辛過ぎる。それに今夜って日曜じゃん。明日の早朝に一人で朝帰りさせるってのもすっげーいただけない。なにより心の準備も。もしかしたら俺とは違って泊まる準備みたいなものもいるかもしれないじゃないか。 突然過ぎる。 何を焦っちまったんだ俺は。後押しがシーツを取り換えたっつーことだけなんて、バカ過ぎる。あまりに愛しくて帰したくない一心で、危うく取り返しのつかない大きなヘマをするところだった。 仙道は言葉の続きを大人しく待っている牧に頭を下げた。 「……ごめん、なんでもないです。やっぱ忘れて。来月の14日、楽しみにしてます」 「仙道? おい、どうしたんだよ……お前、急に変だぞ?」 戸惑っている牧から隠れたい一心で仙道は面を伏せた。 今度は待っても返事はこないと諦めたのだろう牧が腰を上げた。 慌てて仙道は牧を見上げる。 「かえっちゃうんすか……?」 「帰したいのか?」 「んなわきゃねぇでしょ」 「じゃあ、まだ帰らない」 ストンとまた隣に腰を落とした牧は仙道の顔を見てフッと微苦笑を浮かべた。 「なんて面してんだよ」 「だって……」 「俺にとってはお前の言う通りHappy Valentine's Dayだよ。でもな、突然お前にそんな顔をされれば、それも半減だ。お前にだって楽しいと感じてもらわないと。だからほら、言えよ。さっき何か欲しいものを言おうとしてただろ?」 覗き込んでくる瞳が柔らかいから、思わず甘えたくなるけれど。 「いいんです。ホワイトデーにあんたの手作り菓子もらえるから」 無理やり笑みを作れば、褐色のあたたかな手がそっと頬に触れてきた。 その指先はゆっくりと頬から首、首から鎖骨へ移動する。そしてつい先ほど、痛いくらいに熱くなった左胸の上で止まった。 「お前が神棚に収めちまった願いを叶えてくれるのは誰だ? お前か? さっきのは違うだろ。叶えてやれるのは俺なんだろ? なら、俺の神様にお願いしてみたらどうだ」 「しない……言ったって叶わない。叶わなくても諦めれるけど、嫌われんのは耐えらんねぇもん」 「また随分と弱気だな。嫌われるわけないだろ、あんな立派なお供えしといて」 牧は楽しそうにくすくすと笑いながら、離した指先を今度は己の胸にあてる。 「俺の神様は今、素晴らしく上機嫌だ。叶う確率は相当高いぞ」 仙道の耳に唇が触れるほどの距離で囁く。 「願ってみろよ」 低い誘うような囁きに仙道の喉が上下する。 「……神様ってより、悪魔みたいだ。抗えねぇ」 呻くような仙道の呟きを受けても牧は微笑を崩さない。 悔し気に乾いた唇をきゅっと一度噛んだのち、仙道は互いの胸が重なるほどきつく牧を抱きしめた。 耳だけではなく触れ合う部分から彼の胸に住む神様へ直接届くようにと告げる。 「俺の願いは─── 」 * * * * * 体に満ちるこの甘い充足感。 渇望していた形とはちょっと。いやかなり違うけれど。これはこれで素晴らしくいいものだった。これなら準備も道具もいらなければ、泊まってもらわなくても何度もできる。お手軽なのに心も体も大満足。 牧さんも女の子としか付き合ったことがないはずなのに。流石だ。 最終段階のひとつ手前に、こんなイイコトを考えていてくれたなんて。もしかして調べて知ったのかな。いや俺だって調べたからこそ、用意もした。でも深く調べ過ぎた分、敷居が高くなり過ぎて仕掛けられずにいたんだけど。 これからは二人きりで会うたびに、できないかな。そしたらそのうち、すんなりとコトにも及べそうじゃね? でもやっぱ準備が必要なコトだから、そっちはまだまだ先かな……。 けどアレであんなに色っぽい顔や反応を見せてくれるんだから、コトに及んだら…………あ〜ヤバ過ぎ。ちょっと知っちまったせいで、いつの日かが待ち遠しくてたまらなくなっちまったぜ。 「準備さえなけりゃなぁ……」 ベルトを締めなおしながら幸せの余韻溢れる溜息と、つい考えていた余計なことまでまろび出てしまった。 隣でファスナーをあげていた牧が肩越しに振り向き、仙道へ少々冷たい視線を投げてくる。 「お菓子です。お菓子作りのこと。材料や道具揃えたり事前準備が大変だったなーって思い出してただけ。準備さえ大変じゃなけりゃもっと気軽に作ってあんたにあげられるんだけどって話ですよ」 「ふーん……」 見返す表情からは明らかに嘘を見抜いているのが伝わってくる。 まだ赤い目淵の瞳の奥に、微かだが消えない熾火がチラチラと見え隠れしているように感じるのは……俺の都合のいい洞察だろうか。 期待半分で数秒待ったが、彼はそれ以上何も言わずにユニットバスへ行ってしまった。 水音が漏れ聞こえる部屋に残された仙道は、今度は気兼ねなく甘い溜息を天井に吐いた。 * end *
|
||||||
|
|
||||||
|
表だから肝心のチョコより甘い時間は割愛。皆様の妄想で補って下さいねv |